みなさん、こんにちは。
小学校受験でおなじみの「受験対話」総合研究所です。
引き続き、「年長さんクラス」での文章指導の授業風景を紹介します。
これは、ご家庭での「家庭教育」として、またご両親が書くことになる
「志望理由書」や「面接対策」の準備にもなります。
辞書は、「書くもの」「話す」ものです!
年長さんの「文章修業」講座での合い言葉です。
「本は、読むものでなく、引くものです」
つまり、本は「書くとき、話すとき」の資料として、生かせというわけです。
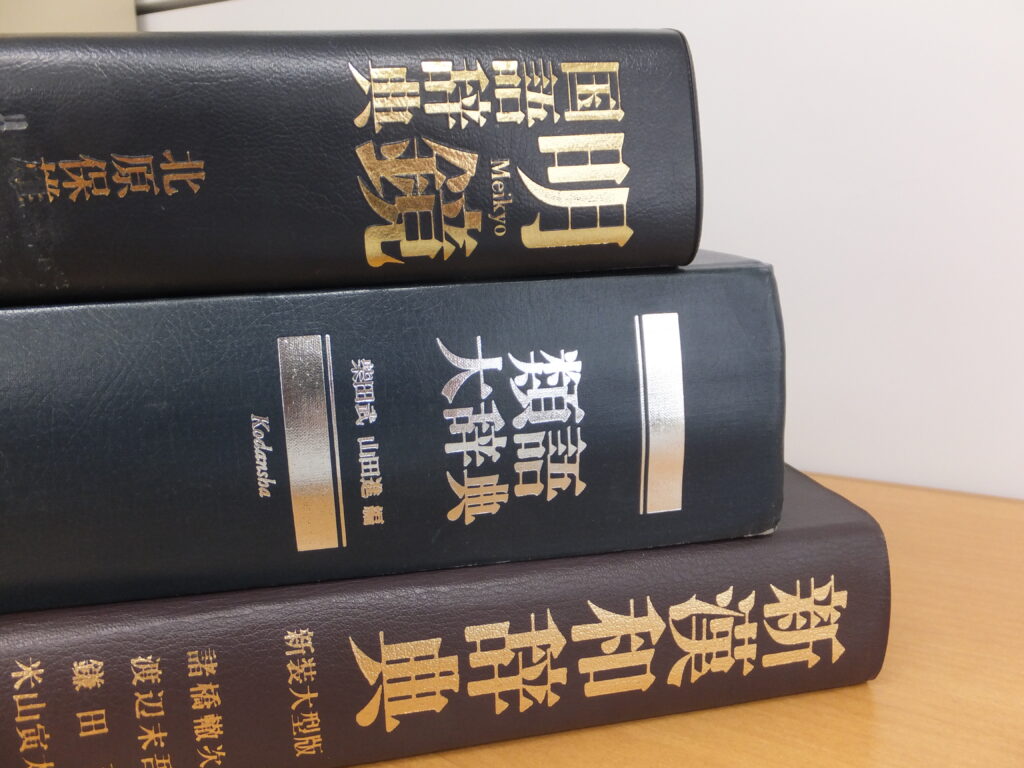
辞書も同じです。
辞書は引くものでなく、「書くもの」「話す」ものなのです。
辞書を読むとは、どういうことなのか?
年長さんたちは、語句や文字、用字用語などについて、少しでも自信がなかったり、
わからなかったら、すぐ辞書や辞典を引きますが(パソコン使用は最後です)、
引いただけでは、なかなか覚えられません。
そこで、「辞書を引いたら、すぐ声に出して読みなさい」と言っています。

辞書を読むとは、どういうことなのか。
日本語には、同音異義語や同訓異字がたくさん含まれています。
子どもたちが、何か調べることがあって辞書を引いたら、すぐ近くにある
同音異義語や同訓異字に目を通します。そこで、自分が使えると思った語や字を探して
「しるし」を付けます。
文字や言葉は、指と口で覚えてください!
たとえば、常用漢字には「あう」という動詞の漢字が3つあります。
「合」「会」及び「遭」です。
用字用語辞典を引くと、それぞれに例文が出てきます。
●「意見が合う」「色が合う」「落ち合う」「話し合う」
●「客に会う」「道で友だちに会う」
●「暴風雨に遭う」などです。

ここから読み取れるのは、
「合」は「ぴったり合う」の意味で、「会」は「人に会う」ときに用います。
「遭」は「不幸な出来事に遭う」場合に使うことがわかります。
「地震」や「交通事故」のときにも使います。
読んで「しるし」を付けたら、その場で原稿用紙に書き写し、その「ことば」を使っておしゃべりします。
年長さんであれば、1度書けば、3くらい辞書をひいた記憶と同じくらいの効果があります。
辞書を引いただけでは、正確に覚えるのはむずかしいので、
3か月くらいしたら、また辞書を開かなければならなくなります。年長さんには、一度で覚えてもらうのがいい。
「文字や言葉は、頭で記憶するものではなく、指と口で覚えてください」と常に言っています。
年長さん、がんばれ!



